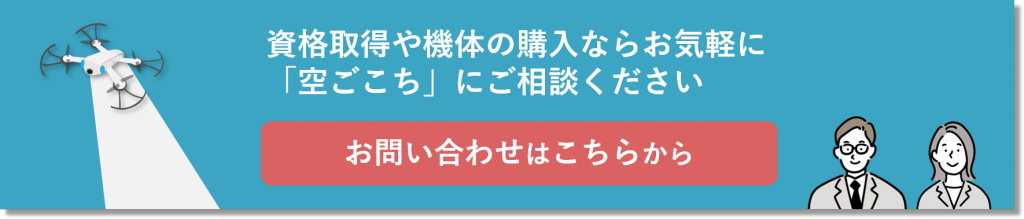ドローンスクール「空ごこち」認定資格コース受講レポート│ドローン×資格取得×法人
JUIDA認定資格(無人航空機操縦技能証明証)は基本的な操縦技術+法律や安全飛行の為の知識をバランス良く取得できる民間の…
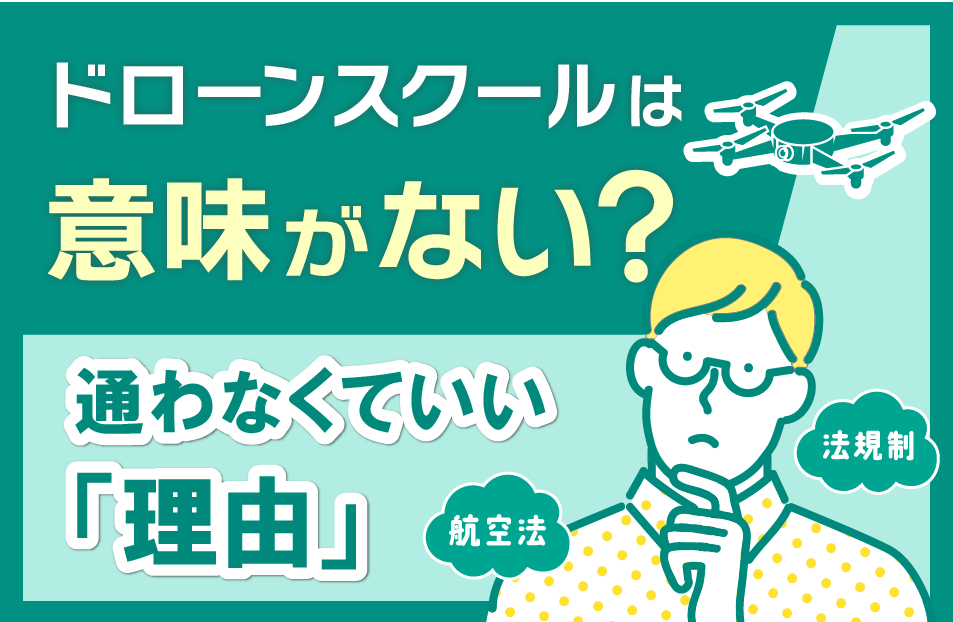
ドローンを趣味で始めたい、あるいは仕事として活用していきたい、そう考えたとき、多くの人が一度は思うのが「ドローンスクールに通わないといけないのか?」という疑問です。
近年では国家資格制度も始まり、やっぱりスクールは必須なのではと感じる場面もあるかもしれません。
しかし結論から言うと、ドローンスクールの受講は法律上も実務上も、必須ではありません。
日本では、特定の条件下でドローンを飛ばす際に「国土交通省の許可・承認」が必要となりますが、それに際して「ドローンスクールの卒業」や「国家資格の取得」が義務づけられているわけではありません。
たとえば、次のような飛行方法は「特定飛行」として許可が必要になりますが、該当する場合でも、飛行マニュアルを自作し、知識と技術の保有を示せば、個人での申請が認められる仕組みになっています。
・夜間飛行
・目視外飛行
・人口集中地区での飛行
・第三者上空の飛行 など
つまり、スクールに通っていなくても、安全対策が整っていれば合法的に飛ばすことができるのです。
ドローンを使って仕事をするうえで大切なのは、「機体をうまく操作できるか」よりも、「撮影や測量などの目的を果たすアウトプットを出せるか」という点です。
たとえば、空撮であれば編集スキルや構図の知識が、測量や点検であれば写真解析や報告書作成の能力が必要とされます。スクールでは基本操作や法律を学べても、業務で本当に役立つ周辺スキルはカバーしきれないことも多いのが実情です。
そのため、実践に必要なスキルを独学で身につけ、経験を積んでいる人の中には、スクール未受講でもフリーランスや法人として活動している例が少なくありません。
現在では、YouTubeやオンライン講座、専門ブログなど、ドローンに関する良質な情報が多数公開されています。さらに、初心者向けの比較的安価な機体でも高性能なモデルが増えており、安全な環境で基本的な操縦技術を独学で習得することも十分可能です。
もちろん、体系的に学びたい、国家資格を最短で取りたいという人にはスクールは有効な選択肢です。しかし、「通わなければ飛ばせない」「仕事にできない」というわけではありません。
車の免許取得も教習所受講が必須ではないのと同様です。今の自分の目的と状況に合わせて、学び方を自由に選べる時代になっているのです。
ドローンスクールは、初心者が短期間で基礎を習得するには便利な環境ですし、国家資格を取りたい人にとっては近道にもなります。しかし、スクールに通わなくても、法律を守り、安全に飛ばし、スキルを磨けば、実務でも十分通用します。
「ドローンを仕事にしたい」「副業で活用したい」と考えている方は、まずは自分の目標と予算、学習スタイルを考えてみるとよいでしょう。ドローンスクールはあくまで一つの手段であって、通うかどうかは自分で選べばいいのです。
ドローンスクールに通わない場合、確かにメリット(費用がかからない、時間に縛られない、実務に即した学び方ができるなど)も多いですが、一方でいくつかの明確なデメリットも存在します。
通わないことによる主なデメリットを具体的に解説します。
2022年から始まったドローンの「国家ライセンス制度」では、登録講習機関(=スクール)を通さずに資格試験を受ける場合、実地試験が必要になります。
この実地試験は決して簡単ではなく、飛行技術に加え、安全確認の動作や飛行前後のプロセスまで、厳密に評価されます。
一方、認定スクールの「修了証」があれば、実地試験が免除されるため、取得までのハードルが一気に下がるという大きな差があります。
つまり、国家資格の取得を視野に入れている場合、スクールに通わない選択は手間や難易度が上がる可能性が高いのです。
特定飛行(夜間飛行や目視外飛行など)を行う場合、個人で許可を申請することは可能ですが、安全対策を詳細に記したマニュアルの作成や、知識・技量の証明が求められます。
スクールを修了していれば、申請時に「技能証明」として修了証を添付するだけで済むケースも多く、審査がスムーズです。
しかし独学の場合、飛行マニュアルをゼロから作成し、知識・技量の裏付け資料を揃えなければならず、申請の難易度と手間が格段に増すのが現実です。
独学では「何が正しく、何が危険か」を判断するのが難しい場面があります。
たとえば、GPSの切り替えタイミング、離着陸時の安全確保、風速に応じた判断など、細かいノウハウや“現場の癖”は動画やマニュアルでは習得しづらいものです。
スクールでは、プロのインストラクターから直接フィードバックを受けることができるため、短期間でミスを修正し、安全に対する意識を高められるという点で、一定の安心感があります。
特に企業や行政案件などでは、依頼先が操縦者の「資格」や「経歴」を重視する傾向があります。
このとき、スクール修了証や国家資格があると、対外的な信頼性の証明になりやすく、選ばれる確率が上がることがあります。
もちろん、実績がものを言う業界でもありますが、初期の段階では「目に見える肩書き」が受注のきっかけになることもあるため、スクール未受講は営業上の不利に働く可能性も否定できません。
ドローンスクールに通わずとも、法的に飛ばすことはできますし、仕事にすることも不可能ではありません。しかし、国家資格の取得、飛行許可の申請、実地での安全確認、営業活動など、現場でのハードルを一つずつ自力で越える覚悟とリスク対応力が求められます。
その負担を軽減し、確実にステップを踏みたい場合は、スクールの受講が「回り道に見えて最短ルート」になることもあります。
通う・通わないは自由ですが、自分の目的と到達したいレベルに応じて、デメリットを許容できるかどうかを判断材料にするのが重要です。
ドローンスクールを受講した人としなかった人の間には、実務面・法規対応・信頼性の3点で、いくつか明確な差が生じます。
それぞれのポイントについて詳しく説明します。
まず大きな差が出るのが、飛行申請のスムーズさです。
ドローンスクールを受講すると、「修了証明書」や「飛行マニュアル」が提供され、それをそのまま国土交通省への許可・承認申請に使えるケースが多くあります。
これに対して、スクールを受講していない場合は、自分で一からマニュアルを作成し、操縦技量の証明書類も独自に用意しなければなりません。申請書類が受理されるまでに時間がかかったり、書き直しを求められるリスクもあります。
つまり、実務で申請の手間とスピード感に明確な差が出るということです。
国家資格(無人航空機操縦士 一等・二等)を目指す場合も、スクール受講者と非受講者の間には差が生じます。
登録講習機関で所定のカリキュラムを修了していれば、実地試験が免除され、学科試験のみで資格を取得できます。一方、スクールを経由せずに国家資格を取ろうとする場合、厳格な実地試験を受けなければならないため、合格のハードルは一気に高くなります。
この差は非常に現実的で、短期間で資格を取得したい人にとっては決定的な違いになります。
スクールを受講した人は、座学と実技を通じて、風速・天候・電波干渉・バッテリー管理・緊急時対応などの安全運航に関する知識を体系的に学んでいます。
それに対して、独学の場合は動画やマニュアルに依存しがちで、知識が断片的になる傾向があります。たとえばGPSが切れたときの対応、フェールセーフ設定、目視監視者の役割など、一見マニアックでも実際には重要な項目を見落とすリスクがあります。
結果として、現場での判断力や事故予防に対する意識レベルに差が出ることがあるのです。
スクールを受講して修了証を持っている人は、企業・行政・取引先からの信頼性が高くなります。資格や実績を求められる場面で、「どのスクールを修了したか」「国家資格を持っているか」が、案件の採用基準になることもあります。
独学者が実力や実績で評価されることももちろんありますが、初対面の営業やコンペでは、やはり“肩書き”がものを言うことが多いのが現実です。
ドローンスクールに行かなくてもよいことは、もう充分お分かりかと思います。
ドローンの操作、実はとても簡単です。
機体を買って、マニュアルを読み、少し練習すれば、ある程度の飛行は誰にでもできます。最近では自動制御機能が進化していて、ほぼボタンひとつで離陸・ホバリング・帰還までこなせるモデルもあります。
だからこそ、多くの人が「スクールなんて必要ない」と思うのです。
そして実際、それでも困らないケースもあるでしょう。趣味でちょっと飛ばして遊ぶ程度なら、法令をしっかり守ってさえいれば大きな問題にはなりません。
でも、そこで終わってしまっていいんでしょうか?
ドローンスクールに通う最大の意味は、「飛ばす技術」を磨くことではありません。
本当の価値は、「知らないと損をする知識」と「現場で活きる判断力」を身につけることにあります。
例えば――
これらは、ネット検索では断片的にしか手に入らず、ましてや現場で即応できるレベルになるには時間がかかります。
スクールでは、その「道筋」が最短で、体系的に学べます。
また、仕事としてドローンを使おうとするなら、「誰から学んだか」や「どの資格を持っているか」が信用材料になります。
例えば、自治体案件や企業の空撮依頼では、機体の登録状況だけでなく、操縦者のスキル証明や講習履歴を求められることも珍しくありません。
独学ではここが不利になります。技術があっても、証明できない。
その差は、チャンスを逃すという形ではっきり現れてきます。
確かに、ドローンは誰でも飛ばせます。
けれど、「飛ばすことがゴール」の人と、「飛ばした先で何かを生み出す人」では、必要なものがまったく違います。
スクールは、単に技術を教える場所ではなく、「目的を達成するための視点」を与えてくれる場所です。
だからこそ、差がつく。
もしあなたが、これからドローンを仕事に活かしたい、あるいはもっと自由に、安全に、堂々と飛ばしたいと考えているなら、スクールという選択肢は“保険”ではなく、“武器”になるはずです。
ご希望があれば、この記事をブログ用に整えたり、具体的なスクール情報を挿入したり、写真や図解つきで展開する形にもできます。どう使いたいか、教えてくださいね。
【最新記事】
ドローンは現在、娯楽、映像制作、航空写真、物流、農業、防災活動、監視、測量など様々な分野で利活用が始まっています。それに伴ってプライバシーや安全上の懸念、飛行制限区域の把握などドローンを飛行させるために必要な知識と安全な飛行技術の習得は必須です。
卒業制作や趣味の空撮、動画制作などでもドローンが活躍し、ビジネスでもホビーでも今後さらに活用用途が広がります。シニアの方や学生の方のご相談、女性のジョブチェンジなども、お気軽にご相談ください。
機体購入のサポートも行っています。お問い合わせはこちら。